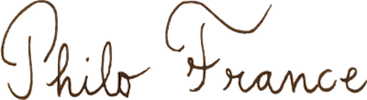アール・ド・ヴィーヴル:フランス人の素敵な食卓とインテリアの秘訣

フランスにいると、インテリアのセンスがすごくよくて、生活のしかたにもセンスのある人をときどき発見します。
運のいいことに、私のまわりにはセンスのいい人がなかなか多いのです。
そんなひとびとを何年か観察して、この人たちの生活がどうして素敵に見えるのか、ちょっとわかってきたんですよ!
というわけで、フランスの素敵なライフスタイルについてのレポートをお届けします。
今回話題にするのは、主に「家のインテリア」と「食卓のテーブル」です。
このふたつが素敵になれば、生活のほとんどは素敵になります。
結論から言いますと、「家のインテリア」で大切なことは以下のとおりです。
- 美的にいまいちなものは置かない
- ものは間に合わせで買わない
- 良い素材のものを選ぶ
「食卓のテーブル」で大切なことは以下です。
- 素敵なお皿とカトラリーを使う
- 食事はできるだけ手作りする
- キャンドルをつける
ではくわしく説明しよう!
「家のインテリア」を素敵にするコツ
おしゃれなフランス人にならい、ダサいもの・安っぽいものは持たない持ち込ませないという熱意が重要です。
この熱意さえあれば、いつか必ず素敵なお部屋に住める…はずです。
コツ①美的にいまいちなものは置かない
そりゃそうなんですけど、しかしこれが意外と難しいんですよね。
ダサいものって案外世の中にたくさんあるじゃないですか。
安っぽい家具とか、意味不明の英文とか仏文がプリントされた物入れとか、100円ショップで便利そうと思ってつい買ってしまったけど結局使ってない謎のグッズとか、昔誰かにもらった自分では絶対選ばないファンシーな写真立てとか、無駄にリアルな犬の顔がプリントされたタオルとか、第一生命の営業の人がくれたディズニーのカレンダーとか、お父さんの知り合いのホールインワン記念の日付入りの皿とか、なんかいろいろあるんですよ。ダサいものは。
こういうものはなるたけ減らしていきましょう。
全部なくすことは不可能だとしても、ダサいものの割合が一定の数値を超えると部屋全体がダサくなることは不可避です。
それから、蛍光灯もダサいです。
蛍光灯自体もダサいし蛍光灯の光もダサいです。
オフィスでは蛍光灯が明るくて便利かもしれないけど、家に帰ってくつろぐ時の明かりはもっと柔らかいほうが素敵じゃないですか。
いい感じのインテリアにしようと思ったら、間接照明の設置は不可避です。
明かりの色とランプシェードのデザインにも気を配りましょう。
コツ②ものは間に合わせで買わない
ものは壊れたりすり減ったりしますから、新しくものを買う必要に迫られることもあります。
しかしその際、「とりあえずこれでいっか」という間に合わせの買い物はダメ。ゼッタイ。
たとえばティーポットが欲しいのでお店に見に行くとします。
そういう時に、もしも
「お店の品揃えのなかからとりあえず何か選ぼう」
という発想があれば、その発想を即刻捨てましょう。
素敵なものが見つからなければなにも買わずにお店を出るべきで、必要であればそれを何度でも繰り返すべきです。
「でもティーポットがないとお茶が飲めないし」
などとついダサいものを買ってしまうと、それはダサい部屋づくりの第一歩になります。
向田邦子さんだったと思いますが、
「良い手袋が見つからなかったので一冬を手袋なしで過ごした」
というエピソードがあります。
この気合が大事です。
ダサいものならいっそ持たないほうがましです。
コツ③良い素材のものを選ぶ
インテリアの印象で大きな割合をしめるのは、やはり面積の大きい、家具や、カーテンや、ソファのカバーやクッションなどであると思います。
つまり素材としては木、布、etcです。
これらの素材が残念だと、お部屋の雰囲気は素敵になりません。
ペラペラしたコーティングの家具とか、合成皮革の椅子とか、化学繊維のカーテンなどがたくさん集まると、どうも安っぽいです。
やはり、本物の木を使った素敵な家具を置きたいし、良質な麻のカーテンをかけたいし、手触りのいい天然の生地のクッションカバーを使いたいものです。
そうすると、ペナペナしたりキヤキヤせず、部屋全体が暖かくて良い雰囲気になります。
「食卓のテーブル」を素敵にするコツ
高級な食べ物を買えることと、素敵な食卓のあいだには特に関連はありません。
お金よりもセンスのほうが完全に大事です。
コツ①素敵な食器とカトラリーを使う
やはりダサいお皿とかグラスなんかを使わないっていうことですね。
チープなキャラクターもののお皿、微妙な引き出物のお皿、なんらかのキャンペーンでもらった飲料メーカーのロゴ入りのグラス、とりあえず安いから買ってしまった飲み口の分厚いもっさりしたグラス、意味不明なプラスチックの柄のついたカトラリー、もっさりした箸などは一発で食卓が台無しです。
こういうものは一刻も早く古道具屋さんに持って行くなどしましょう。
誰か他の人の役には立つかもしれません。捨てる神あれば拾う神ありです。
コツ②食事はできるだけ手作りする
おしゃれなフランス人の食卓の秘訣のひとつは、手作りのものが多い=既製品が少ないことであると思います。
私のまわりのおしゃれなフランス人は、パンを焼いて、焼きたてのパンをかごに移して、素敵な布をかけておいたりします。
お菓子を用意するときは、既製品を買って箱から出したり、プラスチックの包装をとるかわりに、手作りの焼きたてのお菓子をガラスの型から取り出して、アンティークなお皿に載せたりします。
こういうことの積み重ねが、おしゃれ感のもとなんだろうと思います。
それに、パンを焼いたりお菓子を作ったり料理をするというプロセス自体を楽しむことが、今日の世の中ではもはや贅沢なのかもしれません。
素敵な生活をしているフランス人から酵母をもらって増やしてパンを焼いていて、ふと、この作るという過程自体が素敵な生活の一部なのだなと思い至りました。
お金を出せばそれなりに美味しいものは買えるけど、それでもあえて手間をかけて手作りの良さを楽しむところが、酵母の持ち主の素敵な生活の秘訣だと気づいたのです。
そういえば伊丹十三さんが
「既製品のドレッシングやマヨネーズを買う人はその人自体も既製品である」
というようなことを書いていました。
既製品を買うことがあってもいいと思うんですけど、でも、いつでもなんでも買って済ませるとなると、まあそういうことになるだろうと思います。
実際、フランス人は、サラダのドレッシングをよく手作りします。
普段の食卓でもマスタードとバルサミコ酢と塩を混ぜて、そこにオリーブオイルを混ぜて乳化させて、ささっとドレッシングを作ります。
そういうことをしていると、食卓に並んでいるものが既製品でないからして、食卓を囲んでいる人たちも既製品でなくなるのかもしれないですね。
コツ③キャンドルをつける
最後はキャンドルです。
なにはなくともキャンドルです。
心の底から重要です。
まず最初に取り組めることのようでもあり、仕上げのようでもあります。
いつもの食卓にとりあえずキャンドルをつけてみるだけでも、ちょっと気分が変わります。
それとは反対に、インテリアがいい雰囲気になって美味しい料理ができたときに満を持してつけるのもやっぱり良いものです。
とにかくキャンドルをつけましょう。
おしゃれなフランス人は素敵なキャンドルの仕入れ先を知ってるし、素敵なキャンドル立ても持っています。
使い込んでちょっとロウの垂れたあとのある真鍮のキャンドル立てに、ちょっとくすんだピンクとかブルーのキャンドルをさしてみるとか、手のひらサイズの小さなお皿に太めの蜜蝋キャンドルを載せてみるとか、いろいろな方法があります。
そういう素敵なキャンドルを、夕食のときにあれこれつけるのです。
間接照明の部屋なので、キャンドルの光がとてもきれいに見えます。
グラスに注いだワインの色も、蛍光灯の明かりよりもキャンドルや間接照明の光を通したほうが、きれいに見えます。
また、キャンドルをつけるのは夜だけとは限りません。
雨の日のちょっと暗い昼下がりに、キャンドルをつけてティータイムにするというのも素敵だし、日の短い冬の朝に、コーヒーを淹れてパンを焼いて、キャンドルをつけるというのもいいものです。
素敵なものを使って、手をかけて生活すること
今のところ言語化できるのはこんなところです。
これだけでもやってみれば、インテリアと食卓がだいぶ素敵になると思うんですけど、どうでしょう。
ひとことでいうと、素敵なものに囲まれて生活すること、手をかけて生活することが、暖かく素敵なフランス生活の秘訣なのではないかという感じがします。
よい素材の家具や小物で部屋づくりをして、本物のバターを使ってお菓子を作る、というような。
日本でも、自分で梅干しを漬けるような生活ができれば素敵ですけど、そこまでできなくても、ペットボトルのお茶を冷蔵庫から取り出さずに、急須で美味しいお茶を淹れるような生活がいいなと思います。
そういうことを、きちんと選んだ「もの」を使ってするのです。
と、ここまで書いてようやく思い出したんですけど、フランスには「アール・ド・ヴィーヴル (art de vivre)」という言葉がありますね。
「暮らしの技術」という感じの意味の。
私が感心した素敵なフランス人の暮らしって、つまりアール・ド・ヴィーヴルのことですね。
-
前の記事

DQ5のデボラ様は主体的な女性像として案外良くないですか? 2021.01.14
-
次の記事
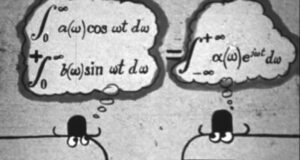
フランスで修士号取得:大学院の勉強が人生で重要すぎです 2022.01.03