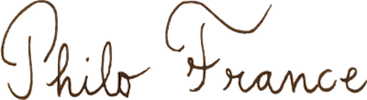【渡仏8年のフランス語力】フランス生活への適応力とは
- 2022.06.20
- フランス

フランスに移住してきて、かれこれ8年ぐらいになりました。
そんなこんなで、最近はフランス生活もなかなかこなれた感じになってきましたので、久しぶりの【渡仏○年のフランス語力】シリーズ(?)とあわせて、移住にまつわる雑感など書き留めてみたいと思います。
渡仏8年(弱)のフランス語力
なるべく客観的なレベルの話からはじめますと、TCFのフルコースでC1を取ってから大学院で2年間勉強しました。
そのあと大学院でも伸びたと思うんですけど、今現在C2ぐらいの力があるのかとかは全然わかりません。
フランスでの学位があるので、今後はもう語学力単体の証明はたぶん必要ないので語学テストは受けませんし、DALF受けるのって面接とか怖いし(えぇ…)。
期間は、全くの仏語初心者からTCFでC1を取るまで4年。
そこから今まででまた4年。
その間それなりに勉強したこともあり、買い物や役所なんかで必要な日常会話にはあまり支障がなく、同居人とそれなりに込み入った話もでき、知らないフランス人どうしの雑談にも少しずつ入れるようになってきました。
しかし雑談は難しいですね。
語彙の手薄な分野だったり、話すのが早い人だったり、若者の語彙だったり、いろいろな難しさがあります。
このへんはもう、いろんな人と話して場数を踏むしかなさそう。
それに、フランスで育ってないために知らないような話題もいっぱいありますしね。
たとえば、日仏逆の例ですけど、パリの日本学科の修士課程にいる学生は日本語がとっても上手いけど、それでも「ねるねるねるね」のCMの話で大笑いとかできんじゃろ?という感じの話です。
共有してるカルチャーが少ないので、こういうのはしょうがない。
けど、同じ地域で育った人たちどうしの雑談だとそういうのが頻出するのもまた事実。
とはいえ、全体的には、自分の考えていることを、抽象的な内容であっても、かなり伝えられるようになったと思います。
フランスでの人間関係への適応
フランス語を勉強して結局なにをどうしたいかって、フランス社会をわかりたいし、そのうえで自分の周囲のフランス社会にそれなりに溶け込みたいんですよ!(突然の熱意)
で、そのへんがどうなったかといいますと、まあぼちぼちです。
もともとが用心深いというか内省的な性格のせいもあるのですが、あたかもシャイな子どもが周囲の大人を観察するような感じで、じりじりとやってます。
この点にかんしてはもう、(高い語彙力を含む)語学力とコミュニケーション力の問題のように思いますから、前者の向上と比例してじりじりとやってます。
とはいえここまできたら、あとは語学力を現場で鍛えることが相当大切ですね。
ある程度フランス語ができるようになったら、
「自分のフランス語で通じるかな」
とか心配しすぎないで突っ込んで経験値を稼いでいくことが必要。
そうやって語彙力とか新しい表現を増やしていくしかない。
それにだいたい、自分の考えていることを伝えないと相手にも自分がどういう人なのかわかってもらえないし、それじゃ個人的な人間関係を構築しようがないし。
しかし日本語でもちょっと突っ込んだ話になると慎重に発言しがちなぐらいなので、勢いつけて突っ込むのってそもそも日本語でも得意ではないんだけど、なにせ経験値を稼がないとレベル上がらないですしねぇ。ハァ(熱意…)
フランス社会への適応
フランス語力が大事だなとつくづく思うのは、
「フランスの人たちは日本の人たちとどのあたりの発想が違っているのか」
「そのためにフランス社会の運営のしかたのどのあたりが日本と大きく違うのか」
などというようなことをつらつら考える場合においてです。
身近な小さい例でいうと、私の個人的な観察なのでアレですけど、日本だと黙ってお茶をすっと出すと、
「まあなんて気の利く、ありがとう」
みたいな感じになるんじゃないかと思うんですけど、フランスでそれやると
「せっかくだけどお茶飲まないんだよね、ごめん」
みたいになることあるんですよ。日本より全然あるんですよ。
それで、なんでかなあと思ってたんですけど、こっちの人って日本の人ほど
「用意する相手に合わせる」
「出されたものはなんでもありがたくいただく」
という発想が強くなくて、逆に
「自分の好きなもの、必要としているものを明確に伝える」
という考えなのかな、って思ったんですよね。
なので、今では
「コーヒーがいい?紅茶がいい?日本茶もあるしハーブティーもあるよ」
みたいな感じで、あなたのリクエストにできるだけ応える用意がこちらにはあるぜ!って感じにしてます。
たぶん、それでうまくいってます。
さらに逆の立場だと、私は渡仏当初、
「お茶とコーヒーとどっちがいい?」と聞かれて、
「どっちでもいいです(用意する人が楽なほうにしてくださいませ)」
みたいな対応をしていたんですけど、そうすると、フランス人におかれましては内心
「いやどっちだよ」
ってなってた気がしたんですよね。
そういうわけで、今では「紅茶がいいです♡」って言って「おいしいです♡」って飲むようにしてます。
そのほうが、私がなにが好きかをわかってもらえて、私もありがたいし、向こうもなんらかの事柄がはっきりとする模様です。
という感じのことを日常生活のいろんなシーンでいちいち考えながら、フランス社会での振る舞いとか心構えをいちいち構築していくわけですが、そのためにはある程度の語学力とか観察力とか柔軟性が必要です。
周辺事情を理解するための語学力、それを「なんで?」って掘り下げる観察力、そこで考えたことを自分に取り入れて自分を変えていく柔軟性。
それらの集合がつまり適応力なんじゃないかなって感じがしてます。
こういうプロセスに興味がない人は、長年住んでてもほとんどフランスに適応していなくて、日本に住んでる日本人とあまり変わらないです。
フィジカル的にはフランスに住んでても、メンタル的にはずっと日本に住んでる感じ。
かなりいい感じです。
というわけで、渡仏8年の現状のご報告でした。
渡仏初期の右も左もわからない状態に比べると、かなりストレスや疲れも減って、快適に生活できるようになったと思います。
-
前の記事
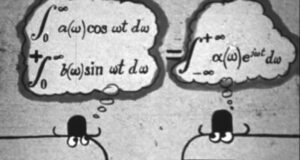
フランスで修士号取得:大学院の勉強が人生で重要すぎです 2022.01.03
-
次の記事

【10年カード新規申請2023/Nanterre】滞仏歴9年の大団円(仮) 2023.06.03