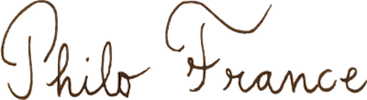フランスの大学院1年目後期:論文を書くことの効能
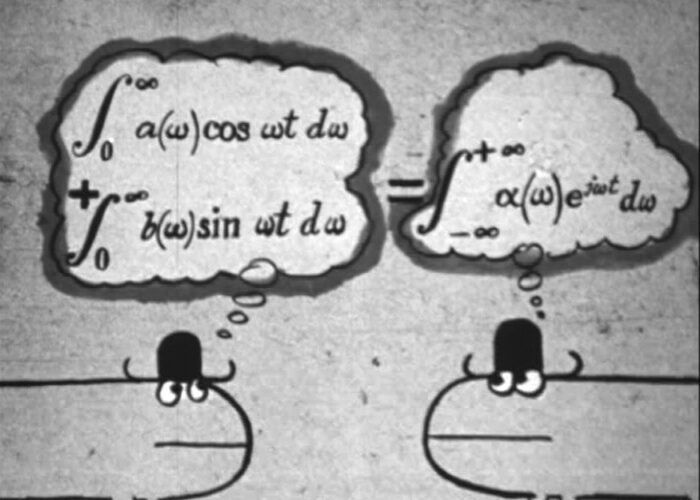
大学院1年目がたぶん終わりました。
「たぶん」というのは、自分のわかる範囲では落とした科目もないし、必修セミナーも全部受けてるんだけど、万一初見殺しみたいな罠に引っかかっていたら、ということを一応心配しているからです。
早く最終結果を学内システムにバシィ!って表示してほしい。
それを確認してさっさと来年の登録料払っちまいたいんだけど…
閑話休題。
前期で勉強したことは『フランスの大学院一年目前期:テクストの読み方』という投稿に書いたのですが、後期はミニ修士論文の提出が大イベントでした。
今回はそのことを中心に、後期で勉強になったことを書き留めておきたいと思います。
修士1年のミニ修士論文
フランスでは修士1年と修士2年が独立していて、
- 修士1年(Master 1 = maîtrise, bac+4)
- 修士2年(Master 2 = master, bac+5)
で、それぞれ別のディプロムになっています。
というわけで、私の行っている学校では修士1年目を修了するために、ミニ修士論文の提出が必須でした。
私も一応日本の大学で卒業論文を書いて卒業したわけですが、しかし、その時の経験は役に立ちませんでした。
もちろん大学によるでしょうが、私の学部の卒論の指導や審査基準は、かなりゆるかったと思います。
今考えたらあれでどうして大学卒業できたんだろう。就職予備校だったのかな
そういうわけで、まともな論文の体をなしていない卒論で学部を卒業してしまったため、今回のミニ論文が本当に大変でした。
「直接フランス語で執筆」か「日本語で下書き」か
ミニ修士論文の大まかな構成を考えて、「いざ書こう」となったのですが、さっそく悩みました。
フランス語で書くべきか、日本語で書いたものをフランス語に訳すべきか、それが問題だ。
思えば、語学学校で250単語ぐらいの短いエッセイを書いていたときは、フランス語で直接書いたもののほうが、日本語で書いた文章をフランス語に訳したものよりも成績がよかった。
たぶんそのほうが、日本語をフランス語に訳する過程で生まれる翻訳的な問題(ニュアンスのズレとか、フランス語にすると通じなくなる日本語に独特の発想の入り込み具合とか)が少なかったからだろうと思います。
こういうことを踏まえた結果、まずはフランス語で書きはじめることにしました。
しかし、この方法は250単語(A4の紙1枚ぐらい)程度の短い文章では通用したものの、40ページを超える論文ともなると、フランス語での思考力の限界にぶち当たるということがわかりました。
つまり、
- 大まかなところでは全体の構成を頭に置きつつ
- 細かなところでは文章に論理的な破綻がないように気を配りつつ
- フランス語のミスがなるっっっったけ少ない文章を書く
ということを同時にやらないといけないわけで、これがまあ非常に難しいのでした。
というより無理でした。
フランス語に集中すると内容がおろそかになり、内容に集中するとフランス語がお留守になる。
「あちらを立てればこちらが立たず」
とはまさにこのことであった。
そこで、日本語で書いたものをフランス語に訳するという方針に変えました。
ここで15ページぐらいやり直したので、たいへん時間をとられましたよ、と。
フランス語が厳密すぎる問題
日本語で下書きすることにしてからは、語学に割いていたリソースも内容に注ぎこめるようになったぶん、いくらか筋の通った文章を書けるようになりました。
しかしそれにしても、フランス語が厳密です。
これってフランス語自体の性格なんでしょうか。たぶんそうですね。
フランス語は日本語よりも、冠詞や指示語を駆使して、いちいち話題にしているものを明確にしなければならないようです。
たとえば「日本人」と書くときも、
- 「全ての日本人」なのか
- 「一部の日本人」なのか
- 「具体的な日本人」なのか
- 「いわゆる日本人」なのか
ということを、明確にしておかないとだめみたいです。
それから、「この」「その」「あの」という表現を使うときも、その言葉が何を指すのか、「読めばあたりはつく」レベルではなく、きっちりと明文化されている必要があります。
フランス語では
「読み手が意図を正確に汲み取れるように、きっちりと隙間なく文章を構築する」
という責任が書き手にかかっている感じです。
日本語はその点、もっと読み手依存度が高いというか、読み手が文脈でいろいろと補って理解してくれる度合いが高い言語のように思います。たぶん。
こういったフランス語で書くことの厳密さに加えて、個人的には翻訳語にも悩まされました。
「契約」や「社会」や「秩序」など、これらの翻訳語の元になったヨーロッパの単語の本来の定義をたどると、自分の日本人頭で理解していることとは違ったりします。
そのために、日本語で書いた文章をフランス語に翻訳して意味が通らなくなったことが多々ありました。
翻訳語ってほんとに難しいですね。
日本語の語彙にすっかり溶け込んでいるんだけど、でもそれはあくまで接ぎ木であって、その根っこや幹を知らなかったりするという。
そしてそのズレがフランス人には見破られているという。厳しい!
論文の分析の方法
日本語とフランス語の間でかなり試行錯誤した論文執筆でしたが、苦労(+フランス人のお力添え)のかいあって、フランス語で意味の通るものは提出できた模様です。
というわけで、ミニ修士論文の評価についての呼び出しがあり、点数と、先生たちによる講評をもらいました。
論文の内容抜きで指摘されたことだけ書いてもアレかもしれませんけど、なるべく一般的に通じる感じでいうと、私の書いたものの問題点は、主に
- 取り上げた作品が作られた当時の時代背景の掘り下げかたが足りない
- 作品から抜き出した問題の原因分析の進め方が性急
ということでした。
たぶん、いろんなことを盛り込みすぎましたね。
もっと分析する事象を絞って、時代背景も掘り下げて、自分が論じている事象の特殊性を似たような事象からどうやって区別できるか、というようなことを考えないとだめだったのかなと思います。
論文執筆はもらえる経験値が多い
論文執筆というのは、
- 信頼できる情報にあたり、
- 様々な角度から問題について検討し、
- それを誰が読んでもわかるように言語化する
ということで、これはたしかに能力です。
そして「言語化する」にあたって、「知識があること」と「知識をもとにある程度の長さの論理的な文章を書くこと」は、また違う能力なんですね。
文章にするには、曖昧な思考を整理して明確にしないといけないわけで。
いやはや、論文を書くってすごいことです。
オンライン授業に移行した後期
大学院の後期は1月末に始まりましたが、3月中旬以降はコロナウィルス対策のために学校が閉鎖されました。
そこからは全部オンラインでの授業、もしくは課題に切り替わりました。
なので今年は、
「交通機関の大規模かつ長期間のストライキで授業がなし崩し的に終了した前期」
「コロナウィルス対策のための大学の閉鎖で対面授業が学期半ばで中断した後期」
という、かなり稀な一年だったと思います。
後期の社会学の授業、すごく面白かったのに途中でオンラインになってしまい、残念でした。
学生からのリアルタイムでの反応や質問があるぶん、対面授業の方がやっぱり情報量が多いですよね。
論文指導も、通常はもっと先生と面談してアドバイスをもらうものだと思うのですが、先生とほぼ会いませんでした。
メールのやりとり何回か、ぐらいです。
とにかくミニ修士論文が大変でした
学部の時はなんだかよくわからずに卒業してしまったので、今回は本当に勉強になりました。
まともな高等教育ってこういうものだったんですね。
大学卒業とか大学院修了とか、いまいちその価値にピンときていませんでしたが、ちゃんとした教育機関で高等教育を受けることには意味があるな、と思えるようになりました。
-
前の記事
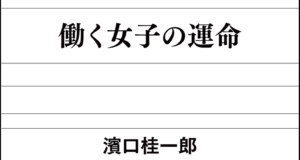
年功序列で男尊女卑の日本型雇用システムはもう時代遅れ 2020.05.15
-
次の記事
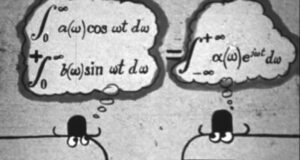
フランスの大学院2年目前期:修士論文の準備開始 2021.01.07